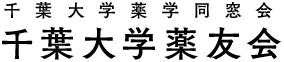薬友会について
薬友会会長 挨拶

薬友会員の皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。2024年4月に薬学研究院長・薬学部長に着任した折に「薬学研究院のリブランディング ~為すべき研究・教育の達成に向けて~」という目標を掲げさせていただきました。具体的には「入学、奉職して良かったと思える学部・研究院」、「地域からも国際的にも求められる学部・研究院」及び「皆が輝ける学部・研学院」を目指して、この一年間の舵取りをさせていただきました。研究活動の活性化といたしましては、医学研究院との研究交流会(2024年6月)、園芸学研究院との研究交流会(2024年11月、松戸キャンパス)、国立医薬品食品衛生研究所との研究交流会(2025年3月、川崎キングスカイフロント)を実施いたしました。特に国立医薬品食品衛生研究所との研究交流会におきましては、同研究所長でもあり薬友会員でもあります本間正充先生にご尽力を賜りましたことをこの場を借りて御礼申し上げます。また薬学研究院研究戦略セミナーを開講し、大型研究費獲得やさらなる医薬連携を志向した活動も行いました。国際活動を含めたその他の活動につきましては、最新の薬友会報の記事をご高覧下さい。
千葉医科大学薬学専門部時代の校章をモチーフとして、千葉大学のスクールカラー(ガーネット)及び薬学研究院・薬学部の部局カラー(るり)を使用したロゴマークを作成いたしました。薬友会のwebsiteから画像データをダウンロードできますので、薬友会の活動の折にご使用いただければと思います。また、ロゴマークのピンバッチも作製しており、薬友会または薬学部(千葉大基金)に一定額以上の御寄附をいただきました方に、返礼品としてお送りさせていただいております。さらに、これまで亥鼻キャンパス内に薬学研究院・薬学部の所在を示す建物の銘板が無い状況でしたが、2025年3月に医薬系総合研究棟IとIIの間の旧亥鼻校舎の屋根飾りが設置されている場所に、薬学研究院・薬学部を示す石碑銘板を設置いたしました。第35号の薬友会報の表紙に写真を掲載させていただきました。是非ご覧ください。ロゴマークや銘板が、教職員、学生及び薬友会の皆様方の帰属意識(Belonging)の向上に役立つことを願っております。
しばらく途絶えておりました薬友会報における広告掲載ですが、薬友会の永続的な活動を維持するため、第35号より再開をさせていただきました。薬友会員の皆様に、事前に十分なご案内ができませんでしたことをお詫び申し上げます。今後も広告掲載を行いますので、是非ともご協力を賜れますようお願い申し上げます。お申し込み等の詳細は、薬友会事務局までお問い合わせください。
薬学研究院・薬学部は、さらなる発展を目指して全力を尽くしたいと思いますので、薬友会員の皆様方の一層のご支援とご協力を宜しくお願い申し上げます。
新しい船出-同窓会から薬友会へ-
平成元年7月8日に千葉大学薬学部創立百周年記念式典と祝賀会が盛大に挙行されたのを機に、同窓会の一層の発展を期すべく組織換えの話が岩城同窓会長(当時)より提案された。その主な根拠は1)大学側と同窓会側の一体感が不足している。千葉大出身でない教官との交流が不足している。2)若い卒業生が同窓会に参加しない。3)組織が大きくなるにつれ、事務組織の確立と資金源の確保が重要となる等であった。この提案を受け、千葉薬同窓会検討委員会が発足した。(中略)検討委員会は5回にわたる会合を重ね、新しい組織作り、会則、事業計画、経費確保の対策の原案を作成した。この案は平成2年10月13日の薬友会総会で議決され、新しい同窓会組織としての薬友会が発足した。薬友会の運営は、会長・副会長を中心として、総務、財務、名簿、事業、会報の5委員会により運営されている。
これからの薬友会に対するご要望をお便りしていただければ、出来るだけ会の運営に反映して行きたいと考えております。ご遠慮なくお知らせください。
また、薬友会の永続的な運営のために、資金確保は最重要課題であります。皆様の御協力を心からお願い致します。
役員
令和7年度役員
| 会長 | 小椋 康光(薬学研究院長) |
| 副会長 | 上野 光一(S47) |
| 内田 武(S56) | |
| 山崎 真巳(教授) | |
| 顧問 | |
| 総務委員長 | 小椋 康光(教授) |
| 財務委員長 | 石川 勇人(教授) |
| 事業委員長 | 山崎 真巳(教授) |
| 名簿委員長 | 中村 浩之(教授) |
| 広報委員長 | 西田 紀貴(教授) |
| 監事 | 矢沢 浩一(S58) |
| 森部 久仁一(教授) |
薬友会沿革
薬学部の最新版の「
会則